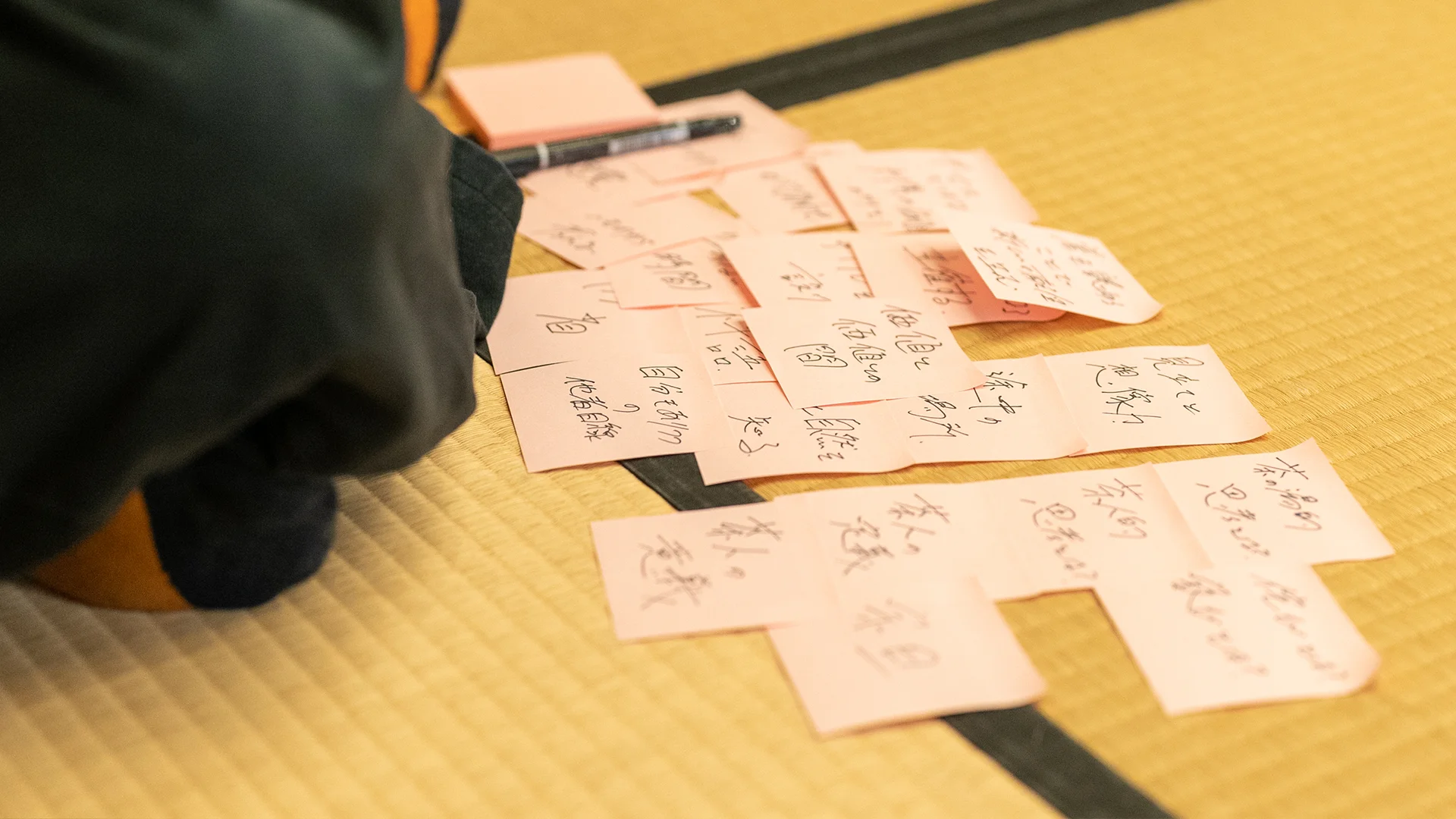「日本の伝統文化を現代的な視点から捉え直す」 茶の湯文化を開拓する 宇野景太
無茶苦茶代表 宇野景太
KDDI research atelierが2021年より始動した「FUTURE GATEWAY」。ここは、KDDI総合研究所がこれまで培ってきた先端技術を活用しながら、先進的なライフスタイルを実践する人々を中心に、多様なパートナーとこれからのスタンダードをつくっていくための共創イニシアチブです。当シリーズ[MY PERSPECTIVE]では、そんなFUTURE GATEWAYに関わる人々の価値観に迫り、共に理想の未来について考えていきたいと思います。
今回は、茶の湯文化を現代に普及させるt'runnerの宇野景太が登場。現代のテクノロジーやアートを茶の湯文化と組み合わせてさまざまな企画を生み出している彼の活動に込められた想いや今後の意気込みについて語ってもらいました。
茶の湯的思考に軸を起き、日本の伝統文化をアップデートしていく

会場提供:SHUHALLY
- FG:
はじめに、宇野さんが代表をつとめる株式会社無茶苦茶(以下:無茶苦茶)について教えてください。
- 宇野:
無茶苦茶は“Respect and Go Beyond”をミッションに、茶の湯にまつわるアートプロデュースを行う会社です。アートを一つの軸としながら、「侘び寂び」「一期一会」といった茶の湯の精神性を現代カルチャーとリンクさせることで、日本の伝統文化の新たな可能性を追求し、文化価値の向上を目指しています。今日のこのお茶室も、無茶苦茶で一緒に活動している茶人・松村宗亮さんがプロデュースしたお茶室です。伝統的なお茶室を基盤としながらもアクリル素材やLED、黒い畳などを使い、“茶の湯の現代アップデート”を空間全体で体現しています。
- FG:
茶の湯とはどのような文化ですか?
- 宇野:
茶の湯は安土桃山時代に千利休が大成した文化で、和の総合芸術と呼ばれています。お茶はもちろんのこと、床の間に飾る花や書、和菓子、陶芸など、日本文化が集合して成り立っているものです。さらに自然や美術が融合している上で、茶の湯は人と人とのつながりを重視した文化でもあります。亭主であるお茶人と招かれる客人がいてはじめて成り立つものですし、どれだけ一期一会の瞬間を楽しめるか、いかに客人にサプライズを与えて場を良いものにできるかという考え方が根底にあるんです。遊び心があるとも言えますね。例えば、掛け軸以外のものをしつらえてみたり、器だけを置いて花を表現したり(想起させたり)することもできます。最低限のルールを守りながら個々の解釈の仕方で変容する、余白を楽しむことができる文化だと思います。
日本文化の余白を通じて、自分の中に問いを持つ

宇野景太:株式会社無茶苦茶代表。“Respect and Go Beyond”をミッションに日本の総合芸術としての「茶の湯」をテクノロジーやストリートカルチャーなど様々な領域と掛け合わせながら日本の精神性や価値観を提起する機会や場をつくり出すアートプロデュース&アーティストマネジメント事業を展開。茶会プロデュースや空間演出、パフォーマンスやプロダクト制作など、現代的に翻訳した茶の湯文化を通して日本文化の新たな可能性を追求している。
- FG:
具体的にはどのようなお仕事をされていますか?
- 宇野:
茶の湯“的”な思考をもとにしたお茶会のプロデュースや商品プロモーションなど、多岐にわたります。印象に残っているのは、ABCマートさんと実施したVANSのPRプロジェクト「スケボーと茶道の意外な関係」です。お茶とスケボーは一見交わることのなさそうなテーマですが、じつはどちらもコミュニティの場として、年齢や性別にかかわらずすべての人を受け入れる機能を持っています。二つの異なる文化に通ずる共通の考え方を見つけ出し、商品PRにつなげることができたのはおもしろかったですね。
- FG:
無茶苦茶では、テクノロジーを使った作品も多く手がけられていますよね。
- 宇野:
そうですね。最近では、空間全体がLEDパネルで囲まれたXR(クロスリアリティ)のお茶会「IPPUKU MAINTE」を東京タワーで実施しました。茶の湯の世界で「お茶室は宇宙」と例えられるのですが、宇宙空間に没入するような、まさに伝統とテクノロジーが融合した体験空間になりました。ほかにもVRを使った映像作品の制作も進めています。茶の湯には一座建立(茶会に集う茶人と客人が心を通わせて特別な一体感をつくる)という考え方があるのですが、テクノロジーの力を使うことで、その精神性をさらに広く共有することができるようになるはずです。それは進化だけではなく文化を「深化」させることでもあると考えています。実際に来てくださるお客様にも「これも茶の湯なんだ」と、新しい考え方に出合うことができる場を提供していきたいです。日本文化には余白があるからこそ、常に自分の中に問いを持ちながら、新しい発見を見つけていくことが大事だと考えています。
- FG:
自分の中に問いを持つ、とは?
- 宇野:
例えば、あるテーマを持ったお茶会であれば、そのテーマを直接的に表現するのではなく、エッセンスとして茶室空間に取り入れていきます。客人ははじめからそのテーマを知ることはなく、パズルのピースを探すように空間を体験することができるんです。このお茶会はなにを表現しているのだろう、と問いを持つことがコミュニケーションの起点になっていくんですよね。さらに、その余白は多くの日本の伝統文化に通ずるものだと思います。受け取り方を鑑賞者に委ねることで、受け手は問いに対する答えを考えたり、自ら作品を作り出したりする。余白があることによって、可能性の受け渡しができるようになります。
曖昧な美意識を可視化し、日本文化の価値をより多くの人と共有する

- FG:
FUTURE GATEWAYの印象は?
- 宇野:
サバンナというコンセプトのとおり、t'runner(ランナー:FUTURE GATEWAYのコミュニティメンバーの呼称)の皆さんは本当に多種多様ですよね。私はt'runnerはお茶人と通ずるところが多々あるなと感じています。3Dプリンターを活用してアップサイクル品を製作したり、クライマタリアンという気候変動に配慮した新しい食のスタイルを一般化していく活動だったり。常に自分で問いを立ててアクションを起こしていくのは、まさに茶人的思考だと思います。そもそも、千利休もそうなんですよ。中国から入ってきた高級品に対して、カウンターカルチャーとして「侘び」という正反対の価値を提案した、日本の初代クリエイティブ・ディレクターのような人物なんです。t'runnerの皆さんと我々がコラボしたときに、どんな化学反応を起こせるかとても楽しみです。
- FG:
とても親和性が高そうですよね。宇野さんがこれから越境していきたいテーマはなんですか?
- 宇野:
伝統文化の翻訳とでも言うのでしょうか。ひとつは「茶の湯の見える化」に挑戦していきたいと考えています。例えば、茶の湯の美意識である「侘び寂び」について、具体的な説明はできずとも、なんとなく感じるものが皆さんのなかにあると思うんです。これからその感覚を、KDDI総合研究所の持つ技術で可視化できないかと考えています。お茶事のどんな瞬間にリラックスしたり、エキサイトしたりするのか。感情の揺れ動きを共通認識として持つことで、もっと多くの方に興味を持っていただくことができるでしょうし、我々も価値を伝えやすくなると思います。
- FG:
現在は、具体的にどんなプロジェクトを?
- 宇野:
余白から新しい未来を想像する「Blank New Day」というプロジェクトを進めています。プロジェクトメンバーの方々と一緒に、茶の湯とKDDI総合研究所のテクノロジーを掛け合わせて、「問いからの想像」を日常化することが現在のゴールです。始まったばかりで行く先はまだわかりませんが、人々の興味関心を具体化していきたいです。他にも3D FOOD PRINTERを活用して、食に関する社会課題解消と食体験のデジタル変革を目指す「Z FOOD PROJECT」との連携も進めています。3D FOOD PRINTERで作る和菓子の食感や味の違いをどのように発見できるのかを試したいなと考えています。マインドフルな茶の湯のエッセンスを含んだ体験から、美意識をどうアウトプットできるか考えていきたいですね。
- FG:
最後に、宇野さんはこれからどのような未来を描いていますか?
- 宇野:
日本の伝統文化に対する興味関心を増やし、タッチポイントを増やすことで文化の価値を捉え直す取り組みをしていきたいです。今年は千利休生誕500年を迎えますが、いまだに「侘び寂び」という美意識は曖昧なものです。それが良いところでもあるのですが、明確に日本の美意識を因数分解し、翻訳したときにどんなものになるのか私自身も非常に興味があります。答えは1つではないかもしれませんが、僕らなりの解を持っていたいんです。その共通言語を現代に持つことで、これからさらに新しい文化の解釈が深まっていくと思っています。
 MEMBER
MEMBER
関連記事
おすすめ記事