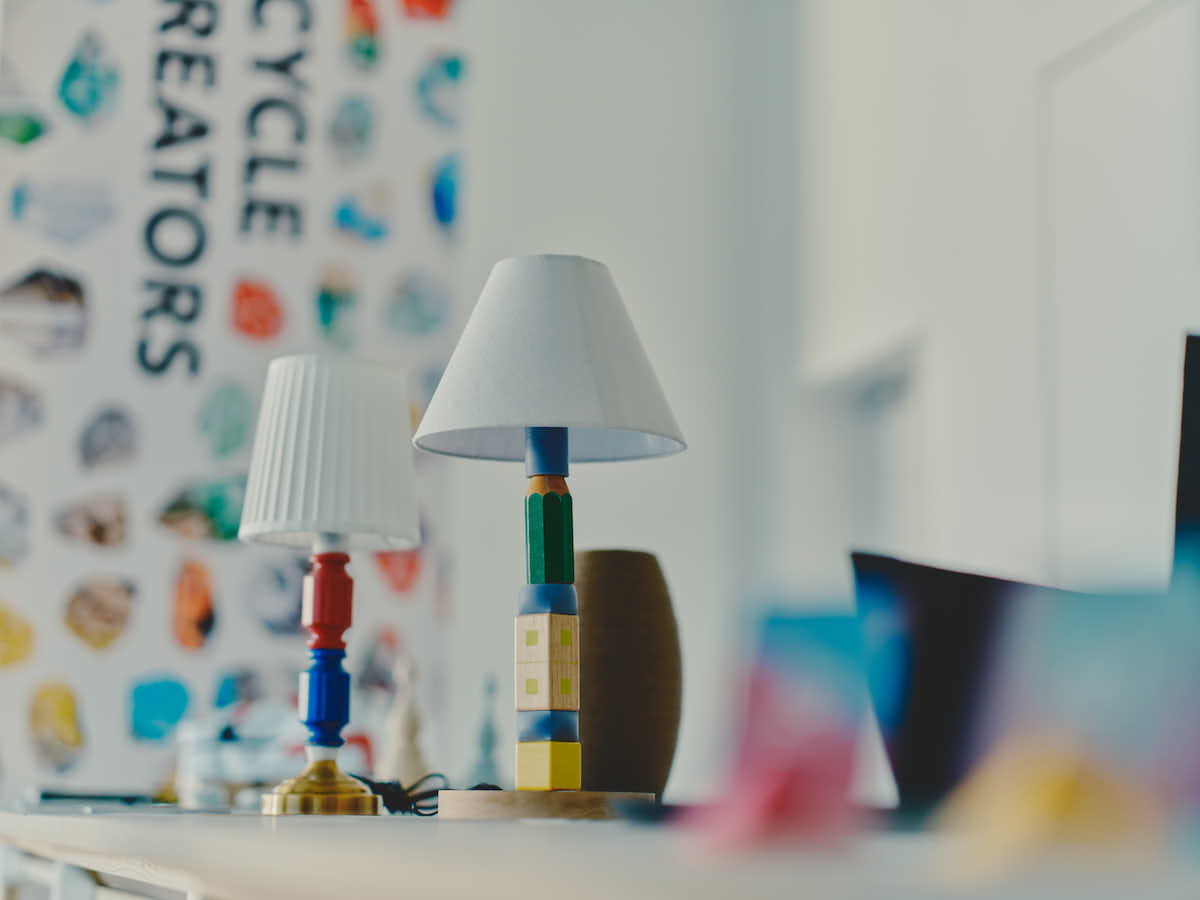



「環境に優しいからこそかっこいい。そんなクリエイティブの未来を創造したい 守田篤史
アートディレクター 守田篤史
2021年より始動した「FUTURE GATEWAY」は、KDDI総合研究所がこれまで培ってきた先端技術を生かしながら、先進的なライフスタイルを実践する人々と共に、これからのスタンダードをつくっていくための共創イニシアチブです。当シリーズ[MY PERSPECTIVE]では、あらゆる分野で未来をつくる活動をしているFUTURE GATEWAYに集うメンバーと共に理想の未来について考えていきたいと思います。
今回は、アートディレクターやプリンティングディレクターとして活躍するt'runnerの守田篤史が登場。デジタルとフィジカルの境界を横断した活動をはじめ、循環型のクリエイティブの探求などにもチャレンジしています。FUTURE GATEWAYでは屋外広告のその先を考える「サーキュラー広告」プロジェクトに取り組んでいるほか、UPCYCLE CREATORSとして2022年10月に開催された「DESIGNART TOKYO 2022」での展示にも参加をしました。そんな数々の活動に込められた想いや今後の意気込みを聞きました。
下町の技術を生かしたものづくりを提案

守田篤史(もりた・あつし):多摩美術大学グラフィックデザイン科卒業後、アートディレクター、コーヒーロースターとしてのキャリアをスタート。アートディレクターと並行してフリーランスのプリンティングディレクターとしても活動。印刷・紙加工とデザインのそれぞれの領域を越えて新しい表現を模索する中、2016年にペーパーパレードに参加。アートディレクターとプリンティングディレクターの2つの視点からの提案を得意とし、作り手とユーザーのより良い関係をつなぐモノ・コトのデザインを企てている。株式会社ペーパーパレード共同代表。JAGDA会員。コーヒーブランド 、キッチンスペース「1 room kitchen」主宰。
- FG:
まずは、アートディレクターとしてのこれまでの活動について教えてください。
- 守田:
ペーパーパレードを始める前は墨田区に事務所を構えていたのですが、渋谷に移って最初は(渋谷にある未来共創拠点である)「100BANCH」に入居しました。ここで(FUTURE GATEWAY発起人の一人である)加藤翼くんと出会ったんです。「100BANCH」では「ヘラルボニー」を立ち上げる前の松田兄弟(崇弥氏と双子の兄・文登氏)とも出会い、メンターが共通だったこともあって、ビジュアルアイデンティティなどのブランディングを担当させていただいたりもしました。それから1年くらい経って、ペーパーパレードとしてユニットを組んでいたタイプデザイナー/アーティストの和田由里子と二人で法人をつくりました。私も和田もそれぞれ個人でアートディレクションなどの仕事を10年以上やっていたので、それぞれの領域を生かしたチームを作れると思ったんです。
- FG:
守田さんの得意分野はなんですか?
- 守田:
墨田区に事務所があった頃、仕事のつながりもあって下町の工場さんと仲良くなりました。そうすると印刷や紙加工の技術・知識が自然と身に付いてきて。下町の技術って本当にいろんなところで使えるんです。こうした知識はほかの方にはない強みなのかもしれません。そしてその知識を携えて渋谷へやってきた感じがします。
- FG:
そうなると、やはりフィジカルなものづくりが多いのでしょうか?
- 守田:
そうですね、ものばっかりつくっていました。ものづくりをするうちにコスト感覚も身に付き、どうすれば持続性のあるものづくりができるのかという観点でコンサルもやるようになりました。でも、やはり圧倒的にポスターや印刷物なんかをつくることは多いですし、実際に制作したものを見ていただいて、新しい案件の相談をいただくことがほとんどです。
カウンターを挟んで生まれる案件

- FG:
ペーパーパレードとしてはどんなミッションを掲げていますか?
- 守田:
紙と印刷の可能性を拡張することをミッションに掲げています。フィジカルとデジタルを横断しながら、いろんなことにチャレンジしたいなと。中心にあるのは紙やグラフィックですが、最近ではファッションデザインなどの案件もあります。紙ものをつくってきたからこそ、別の業界でも新しい角度からアプローチをすることができると思いますし、それが私たちの強みだと思います。
- FG:
そうなると、扱う業種も幅広い?
- 守田:
業種をあえて広げている部分もありますし、いろんな人と話をしているうちに広がっていくこともあります。FUTURE GATEWAYではサーキュラーデザインにチャレンジしていますし、最近は知財や権利などの勉強も増やしています。新しい業種にチャレンジするときには、当然ながら共通言語を理解して話せるくらいには勉強をしています。いろんなことに興味を広げることで、さらに幅広い業種の方のお話を聞くことができているのかもしれません。
- FG:
この事務所も特徴的ですよね。カウンターがあって、ここでコミュニケーションがとりやすいというか。
- 守田:
そうですね。ここへ来てくださって、雑談をするうちに仕事につながるということもあります。もともと墨田区の事務所ではオープンスペースでカフェをやっていたのですが、そのイメージを踏襲して、対面式のカウンターを設置し、キッチンの壁をタイル張りにして、遊びにきたくなる空間をつくりました。いまではデスクに座っているよりこのキッチンに立っていることの方が多いくらい(笑)。来てくださった方にはコーヒーを淹れたり、知り合いがつくっているお茶菓子を出したりして、お話をします。デザイン事務所ってなんとなく緊張するじゃないですか。堅苦しい空間だと本音も出ない。だからこそ、コーヒー屋さん気分で来たくなるような、都会の中で目に優しい空間をつくったんです。
捨てるしかなかった屋外広告に新しい命を

- FG:
FUTURE GATEWAYとの出合いは?
- 守田:
最初はFUTURE GATEWAYの主な活動拠点である「KDDI research atelier」のリーフレットをつくるという相談を受けたところからでした。話をする中でかつてのガラケーのイメージを採用し、折り畳めるポストカードのようなものをつくることになりました。この場所にはいろんな方が訪れて、いろんな個性がぶつかるという話もあったので、表面はレインボーでさまざまな柄を描いたものを100パターン以上つくりました。大きなレインボーの柄をつくってそれを裁断し、裏表で全く異なる柄を組み合わせる。あえて柄をバラバラにして、誰一人として同じものを見ないようにしたかったんです
- FG:
現在ではFUTURE GATEWAYのコミュニティメンバー t’runnerとしても活動をしています
- 守田:
アートディレクターとして依頼していただく仕事もいいのですが、自分たちもプロジェクトを立ち上げたいという思いもあり、t’runnerとして参画しようということになりました。
- FG:
FUTURE GATEWAYでは「越境したいテーマ」というものがありますが、どんな課題を感じていますか?
- 守田:
私はもともと屋外広告に関わっていましたが、あるとき自分がつくった屋外広告を掲載後にもらいたいという相談をしたことがあって。そうしたら「決まりなのでダメです」と。それから屋外広告の素材に興味を持つようになりました。気になって調べてみると、渋谷駅周辺だけでも年間20トンから30トン近い屋外広告が掲示後にそのまま捨てられている。サステナブルじゃないということだけでデザインや広告自体がネガティブに捉えられるのもいやですし、広告のサイクルが早くなればなるほど環境負荷も上がっているのだという重大な課題に気が付いたんです。そこから「サーキュラー広告」というプロジェクトを立ち上げました。「自分のデザインしたものが、貰えずに捨てられるというのが気持ち悪い」という個人的な疑問からスタートし、それが社会性を帯びてきたようなイメージです。
- FG:
具体的にどんなことを実現したいのでしょうか?
- 守田:
捨てられる屋外広告が捨てられなくなる仕組みとか、素材にするようなエコシステムをつくりたいと考えています。現在は屋外広告の素材を活用したバッグやサコッシュ、アートピースなどを自主制作しています。もはや広告のクオリティの追求のためだけに環境を蔑ろにしていい時代ではなくなりました。見た目もカッコよくて、環境にも優しい。そういうコンセプトを含めた提案をしなければならないんです。私はかつて2000年代の広告を見てこの業界に憧れをもった世代ですが、2030年に向けた新しい時代における「かっこいい」基準もどんどん変わっていくと思うんです。
誰かを犠牲にすることのないものづくりの未来

- FG:
2022年10月に開催された「DESIGNART TOKYO 2022」では、アップサイクル家具の製作に取り組むt’runnerの溝端友輔とともにUPCYCLE CREATORSという名称で展示をしました。ここではどのようなことを?
- 守田:
FUTURE GATEWAYには「GOMISUTEBA」というアップサイクルにまつわるプロジェクトがあります。思想が近しいということでジョインし、「GOMISUTEBA」とともにUPCYCLE CREATORSとして企画展示に参加をしました。何かプロダクトを一緒につくったわけではありませんが、情報交換をしつつ共同で企画展示を構成しました。「GOMISUTEBA」と私たちは、目指す方向性は同じでも、バックボーンやアプローチは異なると感じます。
- FG:
どのような違いがあると思いますか?
- 守田:
「GOMISUTEBA」では、アップサイクル文脈で素材を循環・再利用していくことに主眼を置いていると感じます。一方で、私たちはむしろ「ライフハック」に近いのではないかと感じています。「こんなものからこんなものがつくれる」というのは、まさにライフハックの延長です。具体的には、アップサイクルにおいては素材を再資源化しているわけですが、私たちは素材を“素材化”しているんです。広告素材をそのまま切りとって一部だけ使っていくようなイメージですね。
- FG:
素材を素材のまま用いるということですね。
- 守田:
そうです。ただ、広告を素材に使うとなると、もともとのデザイン自体に知財や著作権、モデルさんの肖像権などがあり、そのまま見える形では使えないものも多くあります。そうしたグラフィックをさらにデザインするために、これまで習得した加工技術が生きています。バッグやサコッシュにおいてももともとの柄がわからないような切り取り方、印刷をすることで、元の素材がなんであるかを残しつつ、特定はできないようにしているんです。最近では、こうした取り組みに興味を持っていただき、自治体や企業からの問い合わせも増えました。レコードや服、登山用ロープなど、ありとあらゆるものを使えないかと。そこで、もっと情報共有ができるようにと願って、「一度社会を経由した素材」を扱うプラットフォームとして「openmaterial」というサイトもつくりました。
- FG:
では最後に、今後のFUTURE GATEWAYでの活動も含めて、実現したい未来について教えてください。
- 守田:
これからも既成概念に捉われずに未来的なものづくりをしていきたいですし、業界技術の常識に囚われることなく新しい提案をしていきたいと思います。とにかく、クリエイティブのクオリティを上げるために何かを犠牲にする時代ではなくなりました。これからは、クリエイティブなこと自体が環境にもいいし、かっこいいということを発信していきたい。誰もが笑っていられるようなものづくりを続けたいと思っています。
 MEMBER
MEMBER
関連記事
おすすめ記事















