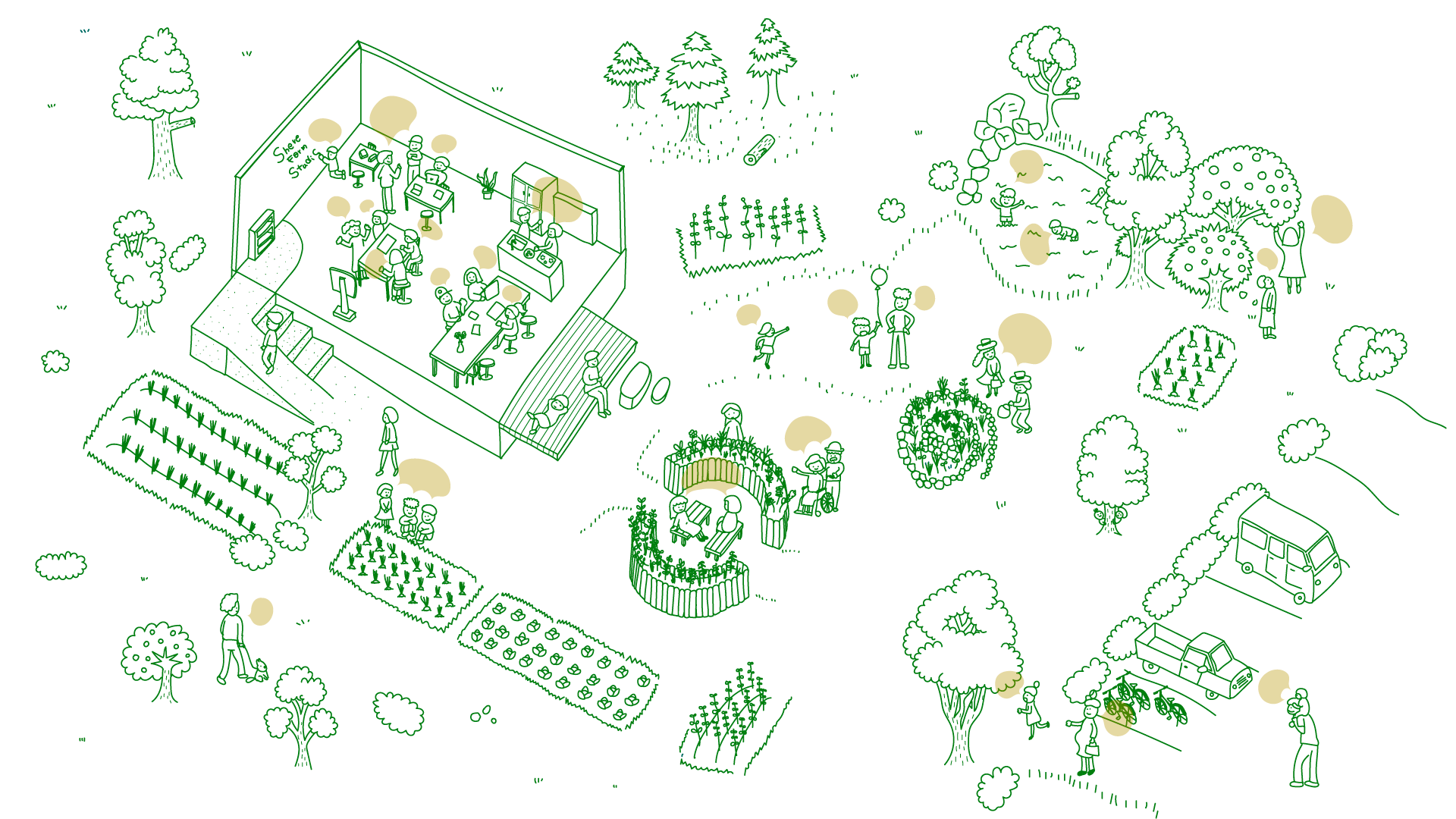「文化回帰の時代に向けて、教養を楽しむ」 社会課題に向き合い続ける 辻 愛沙子
arca 辻 愛沙子
2021年より始動した「FUTURE GATEWAY」は、KDDI総合研究所がこれまで培ってきた先端技術を生かしながら、新しいライフスタイルを実践する人々と共に、これからのスタンダードをつくっていくための共創イニシアチブです。当シリーズ[MY PERSPECTIVE]では、FUTURE GATEWAYに集いながらあらゆる分野で未来をつくる活動をしている方々と一緒に未来社会を考えていきたいと思います。
今回登場していただくのは、社会課題に対してクリエイティブや広告という接点で様々な働きかけを続けているクリエイティブ・ディレクターの辻愛沙子さん。日本における社会課題の現在地と、これからの未来に向けて何を願うのか、お話を伺いました。
純粋な「なぜ?」を忘れずに大人になった

辻愛沙子:arca CEO、クリエイティブ・ディレクター。Ladyknows代表。社会派クリエイティブを掲げ、「思想と社会性のある事業作り」と「世界観に拘る作品作り」の2つを軸として広告から商品プロデュースまで領域を問わず手掛ける越境クリエイター。リアルイベント、商品企画、ブランドプロデュースまで、幅広いジャンルでクリエイティブディレクションを手がける。2019年春、女性のエンパワメントやヘルスケアをテーマとした「Ladyknows」プロジェクトを発足。2019年秋から報道番組「news zero」にて水曜パートナーとしてレギュラー出演し、作り手と発信者の両軸で社会課題へのアプローチに挑戦している。今年5月には未来を語る大人の学び場「Social Coffee House」をスタート。
- FG:
まず、辻さんを紹介するとすればクリエイティブ・ディレクターという肩書きになるんだと思いますが、辻さんは自分の仕事についてどう考えていますか?
- 辻:
いわゆる企画職、クリエイティブ職と呼ばれる分野ですね。クリエイティブ・ディレクターと聞くと「表現する仕事」だと思われることが多いのですが、そもそもの根底にある「社会のあり方を考える」ことが仕事の中心にあるんです。最終的なアウトプット表現は、その中の一つでしかないと思っています。
- FG:
社会のあり方を考えるって難しいですよね。ずっと勉強をし続ける必要がある。勉強をしているという感覚はありますか?
- 辻:
表現やコミュニケーションの仕事をしている以上、学び続けることは前提条件だと思っています。ただ、その上で一個人としての姿勢でいうと、「学ばねば」というより「学びたい」という感覚が近いかもしれません。勉強よりも好奇心に近いかな。色々なことに対して「なぜ?」って思う気持ちがずっとベースにあるんだと思います。
- FG:
今の仕事に至るまでの経緯というか、その好奇心は昔からありましたか?
- 辻:
例えば、小学生のときにランドセルの色が黄色で指定されていたんです。「なぜだろう」と思って先生に聞いたら、「万が一何かあったときにランドセルが黄色だと目立つから」って説明を受けて「なるほど!」と思ったんです。その感覚が今もずっとある。だから、「世直しをしたい」みたいな気持ちよりも、当時の興味の対象が学校から社会にまで広がっただけで、あの頃の「なぜ?」に限りなく近い感覚のままで生きているんだと思います。
「クリエイティブアクティビズム」を実践する

- FG:
お仕事をする上で、意識していることはありますか?
- 辻:
思想がマッチするか、世界観を表現しうる場所かどうか、その二軸を意識しています。以前は世界観に比重を置いていたんですけど、企画段階で「女性ならではの企画を下さい」って言われることがあって。「女性ならでは」ってなんだろうと思ったんですよね。もともと女子校に通っていたので性別を意識する場面が少なかったし、学生時代に海外にいたので性別の前に人種もルーツも母国語も全部が違う環境だった。働くようになっていきなり「女性ならでは」と言われてモヤモヤを感じるようになり、少しずつそういったステレオタイプやバイアスを打ち壊す表現を手がけていくようになりました。
- FG:
そのモヤモヤが言語化できたというか、自分の中ではっきりしたきっかけはありましたか?
- 辻:
3年ほど前に、書籍のご依頼を頂いたときですね。日常にある生きづらさを抱えながらも生きていけるということを伝えたかったのに、編集部から提案されたのが「女子大生なのにクリエイター」というキャッチコピーとピンク色の装丁だった。「なのに」ってなんだろうって思いました。自分の中ではその二つが並ぶことには違和感がなかったんです。だけど、そのモヤモヤした感覚をどれだけ伝えても話が噛み合わなくて、ショックを受けて。そこから明確に仕事において思想がマッチするかを考えるようになりました。
- FG:
辻さんの中では社会課題が大きなテーマになっているわけですが、それは仕事でもあるし、ある意味では社会活動でもある気がします。
- 辻:
「クリエイティブアクティビズム」という言葉を掲げているんですが、私は「アクティビズム」という言葉がとても好きなんです。社会活動に限らず、あらゆるアクションはアクティビズムになりうると思っていて。その中でも広告という手段を使うと、変化の総量が大きい。それは世の中に対してもそうだし、その広告を出した企業で働く人たちにとっても変化を起こすことができるから。広告を見て「うちの会社ってこういうことやってるんだ」って思えるじゃないですか。
- FG:
なるほど。一方で、広告の仕事を通じて課題感というか難しいなと感じることはありますか?
- 辻:
社会課題を企業が発信することについては、とても難しいなと感じます。実態が伴わないままに企業が社会課題へのアプローチを発信することで、課題を企業利益のために消費する”悪しき商業利用”になってしまうケースがあるんです。それを「ウォッシング」といいます。企業が世論を代弁するという形式ながら、生活者のサポートどころか、企業が個人の小さき声を奪ってしまうこともあって、それは違うと思うんです。世論って個人個人が怖い気持ちを乗り越えて発した声によって作られているわけじゃないですか。だから、企業は後方支援をするべきだと思うんです。私は仕事して企業のお手伝いもするし、一方では個人としても発信をする。自分が個人としての発信を続けることで、企業の仕事においても商業利用的にならないよう感覚を保っておきたいんです。
「大人の教養」を語り合う場所を

- FG:
今年新しく立ち上げたSocial Coffee Houseというスクールについても、ぜひお話しを聞きたいです。コーヒー片手に語り合う「大人の学び場」というコンセプトのもと、ジェンダーや政治、環境、性教育などを語る場を作っています。これは、どういう経緯で始めようと?
- 辻:
仕事の相談でエシカルチェックを頼まれることが多いんですね。私としてはクリエイターやジェンダーの視点から話すことはできても、他の分野になると専門的な知識はない。だから、エシカルチェックをする有志の団体を作りたいなと思ったのが最初でした。あと、よく夜中に思い立って、自分が考えていることを話すためにツイキャスをやっていたんです。そういう時間があることで考えが整理されるし、そういう場所がもっと必要だと思いました。
- FG:
自分と向き合って、考えを整理していたんですね。
- 辻:
そう。大人になると「自分ってなんで生きてるんだろう」みたいな内向きな話がしにくくなるじゃないですか。誰でも人生の中で一度は考えるはずなのに、大人になると青臭い話になってしまって、もっと“外向き”な話をしなければいけなくなる。でも、みんな本当は考えているし、話したいんですよね。内にこもりにくい社会の中で、学ぶことと語ることの両方を行ったり来たりできる、心理的安全性が保たれた場所を作りたいと思ったこともSocial Coffee Houseにつながっています。
- FG:
学びたい、語りたいという思いには、自分の経験も関係している?
- 辻:
知らなくていいなら知らないままで過ごしていたかったとも思うけれど、女性に生まれたからこそ気づく不均衡や差別があるなと感じることがあって。例えば「女のくせに」みたいな。それならば、別の人の視点だからこそ気づく痛みだってあるはずだと思うんです。でも、それを学ぶ機会もないし、精一杯想像することしかできない。そういう他者の視点に対する想像力を養い、学ぶ場が必要だと思ったんです。そしてそういうことを、ちゃんと心理的安全性の保たれている環境で語りたいなと。
- FG:
実際始まってクラスにも参加させてもらっていますが、参加されている方の熱量がすごいですよね。始めてから少し時間が経って、率直にいかがですか?
- 辻:
完璧じゃないと世の中に出しづらい今の風潮って、とても生きづらいじゃないですか。全てを理解していないと発信してはいけない、という緊張感があるというか。でも、全てを分かっている人なんて当然いないわけです。Social Coffee House自体も、そういう意味では完璧に決めきってから始めようみたいな感覚はあんまりなくて。まずはターゲットを絞らないで始めてみようと話し合って、どんな人に届くのか見える化しないままローンチしてみたんです。実際には10代から50代までさまざまな年齢層の方が参加してくださっています。でもやっぱり、圧倒的に若い人が多い。これからはそうした人たちが少しでも生きやすくなるために、意思決定層にいる方々をどうやって巻き込んでいけるかを考える必要があるなと思っています。完璧じゃなくても、やってみてわかることってたくさんありますね。
文化回帰の時代に向けて

- FG:
社会課題を扱う仕事のことから始まって、それを学び語り合うためのスクールのことを聞いてきました。最後に、これからやりたいことだったり、そのためにKDDIが持つ技術で生かせるようなアイデアってありますか?
- 辻:
今はインスタントな文化があまりにも溢れすぎて、偶発的な文化との出会いがほとんどなくなっている気がします。ビジネス的に淘汰されていくのは仕方がないけれど、街として、小さくても残っていくべきものってあると思います。例えば、渋谷にたくさんあったミニシアターがどんどんなくなっていったじゃないですか。そうした空間を活用して、KDDIのネットワークを使った5Gエンターテイメントの体験施設みたいなものが作れるんじゃないかと。渋谷で言えば、行政や民間も巻き込んで一緒に文化のインフラを作っていけるんじゃないかと思っています。
- FG:
文化を守りながら、未来を作っていくと。
- 辻:
未来って聞くと、文明寄りなイメージがあるじゃないですか。歴史の中では文明と文化の時代が交互にやってくると言われていますが、これからは「文化回帰」の時代が来ると思っています。インターネットが出て、便利になった分だけ私たちが日常で失った文化を、人間らしさをもう一度取り戻していくっていうのが、これからの未来のあり方だと思っています。それって実はAIの発達と同義だと思うんです。AIが発達すればするほど、みんなアイデンティティを失って、人間らしさを考えるようになる。その時のために、人間らしさに触れるとか、役に立たない経験をするとか、文化形成のトレーニングをしておく必要がある。そういうことを大事にできる場所を作れたらいいなと思います。

 MEMBER
MEMBER
おすすめ記事