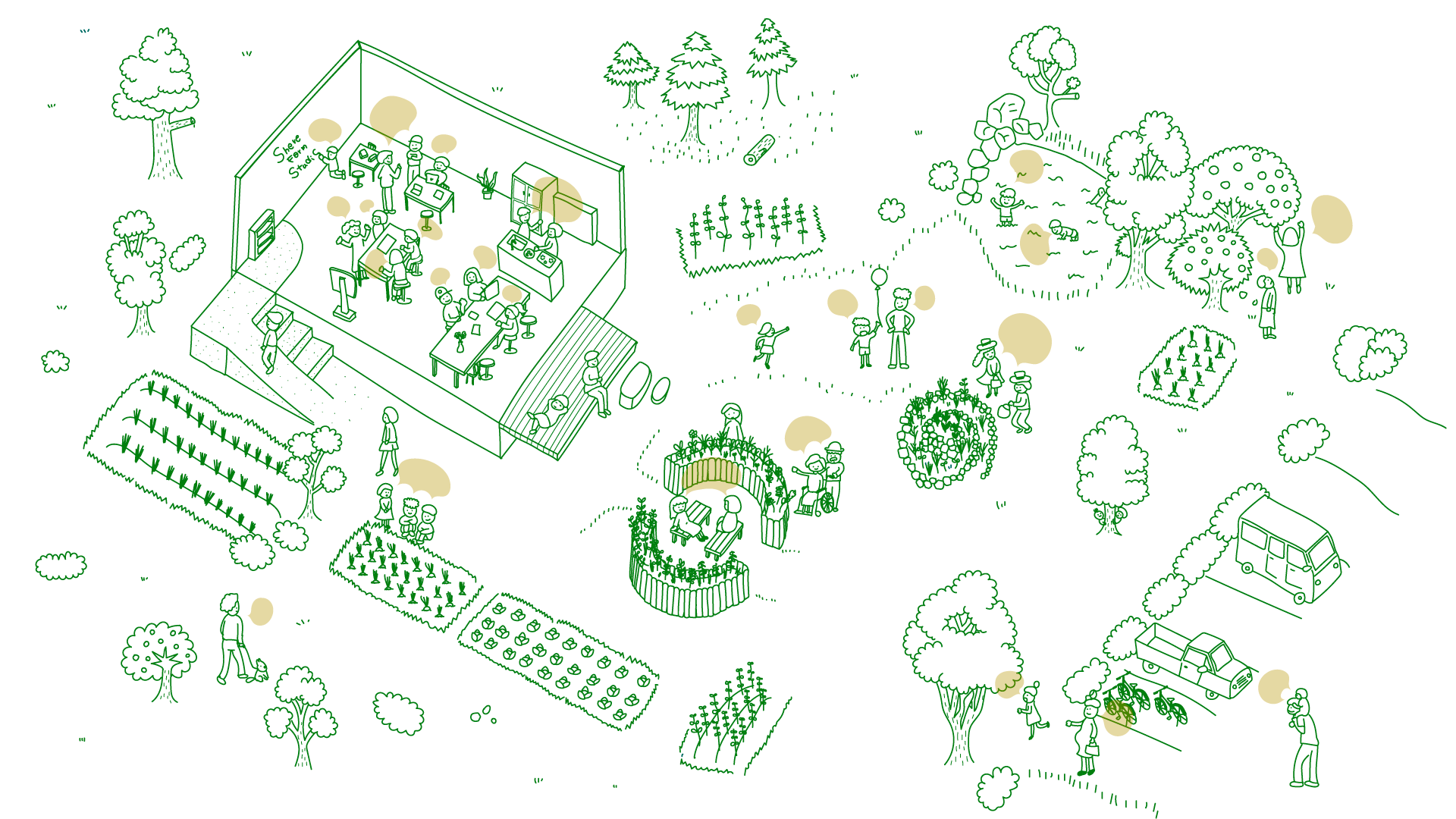「集中したいもののために、勝手に集中できるユートピアを」 JINSで働き方を考え続ける 井上一鷹
株式会社Think Lab取締役 井上一鷹
2021年より始動した「FUTURE GATEWAY」は、KDDI総合研究所がこれまで培ってきた先端技術を生かしながら、新しいライフスタイルを実践する人々と共に、これからのスタンダードをつくっていくための共創イニシアチブです。当シリーズ[MY PERSPECTIVE]では、FUTURE GATEWAYに集いながらあらゆる分野で未来をつくる活動をしている方々と一緒に未来社会を考えていきたいと思います。
今回登場するのは、JINS MEMEの成果をもとに生まれた会員制のソロワーキングスペース「Think Lab.」を率いる井上一鷹さん。この一年で最大の変化とも呼べる「働き方」について考え続けてきた井上さんは、2030年の仕事のあり方をどう見ているのでしょうか。東京・銀座に新設されたThink Lab.でインタビューしました。
コロナは働き方の変化を加速させた

井上一鷹:株式会社ジンズ 執行役員 事業戦略本部 エグゼクティブディレクター 兼 株式会社Think Lab 取締役、Newspicksプロピッカー(キャリア・教育関連)。大学卒業後、戦略コンサルティングファームのアーサー・D・リトルにて大手製造業を中心とした事業戦略、技術経営戦略、人事組織戦略の立案に従事後、ジンズに入社。商品企画部、JINS MEME事業部、Think Labプロジェクト兼任。算数オリンピックではアジア4位になったこともある。著書「2021/04/07発売:深い集中を取り戻せ」「集中力 パフォーマンスを300倍にする働き方」
- FG:
あらためてになりますが、Think Lab.という場所の特徴について教えてください。
- 井上:
端的にいうと、一人になって集中する場所。世界で一番集中できる場所を目指しています。この場所をつくるために、JINS MEMEというデバイスであらゆる集中のデータを測っているんです。まわりの植物がどれくらい目に見えると集中が続きやすいかとか。こうしたデータに基づいて、たとえば、音に関しても耳で聞こえる音だけではなく、肌でしか感じないような音まで再現しています。データをもとに「集中」を研究して、エビデンスがあるものを機能として織り込んでいく。それがThink Lab.の基本思想です。
- FG:
それは、どのような経緯で生まれたのですか?
- 井上:
かつてJINS MEMEを普及させるために僕が眼鏡を持っていろんなところに行って「こういう働き方って良いよね」というPRをしていたんです。それで、ある時「JINSはどうなんだ」と思って測ってみたら、ひどかった(笑)。それから集中に関するデータを集めるようになりました。その結果をもとにいろんな企業の働く環境の設計コンサルをやり始めたのが原点でした。事業としてというよりもJINSのなかで副業的に始めたことでしたね。
- FG:
今でこそ働きやすい環境づくりは大きなテーマになっていますが、コロナが流行する前からそういうことをやっていたと。
- 井上:
コロナが流行する前から働き方は変わり始めていました。コロナはそれを加速させたのだと思います。働き方に関してはそもそも昔から無駄が多くて、一時間どこかの会社で打ち合わせしたら、前後に30分ずつくらい無駄な時間が発生してしまう。それで、とりあえずカフェでパソコンを開いて仕事をしていたわけですが、カフェの椅子って、どう考えても1、2時間が集中の限界。この銀座のThink Lab.はまさにそういった方に向けて、ちゃんと集中できる環境を整えたものになります。銀座という人口密度の高い場所に、茶室のような集中環境をつくりました。
- FG:
コロナを経てなお、リアルな場所をつくったわけですが。
- 井上:
コロナで人が外に出なくなった頃には、在宅勤務用の集中場所として段ボールで簡易的に組み立てられる「Think Lab HOME」というのをつくったんですよ。あの頃は来年がどうなってるか全然わからない状態だったので、再生紙を使って一時的な自宅の作業スペースをこしらえた。でも、どうがんばったって、サードプレイスとしての家って70点が限界だと思いました。利用者に話を聞いてみると、結局は家でずっと仕事をしていても環境が変わらないので、外に出ることによる“非日常”を求めていたんですよね。だから、気分の上がる銀座という場所にこもることには意義があると感じました。
あらゆるものが自由になり、自分の人生に集中できる

- FG:
コロナと働き方という話に戻ると、この一年間でズバリ何が変わったと思いますか?
- 井上:
一言で言うと、あらゆるものが自由になった。まず、どこで働いてもおかしいと言われない社会になりました。東京都としてもテレワークを推進していたわけですが、コロナによって結果としてその目標を実現できてしまったんです。そして、TPOのうちの「P」が自由になったことで、TとOもつられて自由になる。従来の管理体制がなくなったことで、固定された時間で働くということも変わりましたよね。そうして、場所と時間が自由になり、副業が進んだんです。それが基本的な変化だと思います。
- FG:
それは、働く人にとってはいいことだったのでしょうか?
- 井上:
嬉しくてしょうがない人が2割、困っている人が8割ですかね。前者は決めることが楽しい人、後者が決めてほしい人だと思います。結論としては、自由度の上がった社会では、うまくいく人とそうでない人がはっきりと分かれてしまいました。そして、変化を楽しめる人にとっては最善の働き方になったということです。
- FG:
そうなると会社のあり方も変わってくるわけですよね。
- 井上:
今までの会社は「ミッション(思想)」と「ファシリティ(設備)」を提供していたわけですが、ファシリティを提供する動機がなくなった。会社をアイコンにする時って、だいたいはビルの絵を描いていましたよね。今はもう違うんです。
- FG:
なるほど、今まではファシリティこそが会社の象徴だった。
- 井上:
そうです。だけど、これからの会社は「ミッションの塊」になると思っています。ミッションを束ねているものが会社で、そこに面白がって参加するのが個人。ミッションを果たすために必要なファシリティ、つまり、働く場所とかパソコンとかは個人が選べばいい。決められたアイテムを使うルール固定の競争から、ドーピングし放題の競技になったようなものですね。投資によって得たスキルやノウハウに、ファシリティやツールを自由に掛け算して最大限のアウトプットを出す時代になったんです。
- FG:
自由になったからこそ選べるし、選ぶ意味が出てきたんですね。そう考えると、なぜ今まで選べなかったのかとも思ってしまいますね。
- 井上:
そうですよね。ワクチンの普及を見越して「またどうせ以前の働き方に戻るだろう」という論調もありますが、それは良くないと思います。昔のほうがよかったこと、今の方が良いことをちゃんと自分たちで分解して残していくべきですよね。
- FG:
Think Lab.的な思想から言うと、会社が提供するファシリティがなくなるということはチャンスですよね?
- 井上:
もちろんです。Think Lab.のブランドコンセプトは「LIVE YOUR LIFE」。自分の人生に集中してほしいということなんです。楽しいことに「楽しいから」以外の理由ってあんまりないじゃないですか。私たちはそこに向き合う人々を支えたい。自由だから選べる、選べることを楽しむという人は能動的に選択しているわけで、自分の人生を生きているんだと思うんですよね。そのために僕らができることを選択肢として社会に提供していきたいわけです。
勝手に集中できる理想の環境とは?

- FG:
では、これからの働き方はどうなっていくと思いますか?
- 井上:
「自由度が上がる」と言うことに尽きると思います。そして、能動性のある人のほうがより楽しく仕事ができる時代が来る。僕の話をすると、新規事業の開拓をやっているので、もともと抑圧してもしょうがないような職種なんですよね。今日思っていた仮説が明日変わるなんてこともよくあるので、自由であることを楽しめないと意味がない。だから僕のように新規事業をやってきた身としては、そういう働き方が一つの正解だと思っているんです。
- FG:
それはフリーランスのような自由な職種に限った話でしょうか?
- 井上:
今の社会全体を見ると、お金があるにもかかわらず、人が足りていない感じがします。銀行は融資をしたいのに、金利が安くても誰も借りてくれない。だからCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)をつくってお金をプールしたりしているけれど、投資しようにも良いベンチャーがなかったりする。だから、企業としても新規事業開拓の求人募集をしているところが増えています。能動的に働きやすくなった社会で、新規事業をやりたい企業も増えている。すると、イントレプレナー(企業内起業家)が輝く時代が来るんです。サラリーマンという形で、起業するほどのリスクを抱えることなく、価値創造に本気で向き合える。それって、考えることに集中できるという点ではめちゃくちゃヘルシーだし、幸せだと思うんです。
- FG:
では、これからの働き方をサポートしていくために、KDDIに望むことやともに共創できるアイデアはありますか?
- 井上:
これまで、洋服もメガネもそうですが、みんながそれなりに良いと思うものを大量生産してきたわけです。それは最大公約数的なモノづくりが続いていた時代だと思うんですけど、これからはやっぱりパーソナライズな世界に向かっていくと思います。その最たるものが、ナッジだと僕は考えています。
- FG:
ナッジ?
- 井上:
言うならば、良い選択を自発的に取れるように手助けをすることです。たとえば、Think Lab.に来てくださるのは集中したいからですが、それってすでに「集中を意識している」状態じゃないですか。そうじゃなくて、自動的に集中したい状態になるような体験設計が必要だと思うんです。そのためには、個人が持っているスマホが起点となって、キャリアの持つ横断的なデータ基盤を生かしていくしかありません。身につけたスマホの情報をもとに、働く環境が自動的に最適化される。その結果、自然と集中できる環境が無意識のうちに作られるんです。私たちはJINS MEMEという端末のデータを解析しているので、そこに幅広いビッグデータを掛け合わせることでナッジを実現できるのではないかと。そして、そんな意思を使わずに最適化できる場所があると、その分の“意志力”が残るので、本当の意味で自分が意志力を込めたいときに使えますよね。
- FG:
何も考えないわけではなくて、ちゃんと考えたいことのために残しておくんですね。
- 井上:
そうです。集中したいもののために、勝手に集中できる状況ってユートピアじゃないですか。自分のデータによって自分の身の回りの環境を変えていくユーザーセントリックな世界は本当の意味でのいい未来になるんじゃないでしょうか。

 MEMBER
MEMBER
おすすめ記事